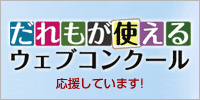アクセシビリティメモ/「改正迫るウェブアクセシビリティの規格(JIS X 8341-3)の改正のポイントと動向」 http://www.ark-web.jp/accessibility/2399.html
アクセシビリティメモ/「改正迫るウェブアクセシビリティの規格(JIS X 8341-3)の改正のポイントと動向」12月3日に行なわれた、
第16回ヒューマンインタフェース学会セミナー
「改正迫るウェブアクセシビリティの規格(JIS X 8341-3)の改正のポイントと動向」
http://www.his.gr.jp/activities/seminar/read.html?016.cfp
に行ってきました。以下はそのメモです。
※なおセミナーの内容は進行中のものであり、実際には変わる可能性もあるとのことなのでご注意。
JIS X 8341-3の紹介と改正のポイント †
主査、渡辺隆行(東京女子大学)さんによる概要説明。
- 緑本 http://www.amazon.co.jp/dp/4839922209
- JISに関わったみなさんが翻訳で参加した良本。
- なのに売れなかったらしい。。もう版元にもない。
- 本屋にあるのが最後なので、見かけたら迷わず買え。
- [!]JIS公示は、2010年度第一四半期(=来年5月か6月?)見込み。
- なのでJIS2009でなくJIS2010と呼ばれていた
- 審議に時間がかかっているらしい。。
- Understanding, Techniqueの日本語訳を進めており、JIS公示と同時期に公開する
- 協力者募集中とのこと
- 年度末(=3末)に途中経過を公開
- 英語できなくてもできることないですか?^^;と聞いてみたら、やはり翻訳が一番欲しいらしい。
- ガイドラインの雛形や、実装の統一見解もあわせて発表したいと考えている
- 今年度中にNPOをつくるらしい
JISの技術情報 †
(渡辺昌洋(日本電信電話株式会社)さんの、図版によるわかりやすいまとめがあった)
こういう資料を用意する予定だそう。
| JISの文書 | WCAG2.0の文書 | 文書の内容 |
| JIS8341-3X | WCAG2.0 | 原則 |
| JIS解説書 | Understanding WCAG2.0 | 詳しい説明。どの実装方法を使うべきか |
| JIS実装方法集 | Technique WCAG2.0 | 具体的な実装方法 |
これ以外に、
- テストファイル
- アクセシビリティサポーテッド情報(ブラウザや支援技術の機能情報)
を用意する予定とのこと。
JIS実装方法集 †
植木真(インフォアクシア)さんの説明。
- 現在、翻訳中
- 350近くの実装方法、不適合事例
- TechniqueではHTMLの記述ばかりだったが、Flash,PDFの実装方法もAdobeから提出されW3Cで審議中。
- ブラウザのサポート情報の記述も?
- 参考リソースには日本語の記事も?
- スキップリンクの新しい要件
- よく隠しで入れているが、
- 常に表示されているか、フォーカス時に表示される必要があるようになった。
- 晴眼者かつキーボードのみで操作している人向けに
- 「達成基準を満たす実装方法」、についての記述
- 実際に利用者にとって利用可能であることを確認しなければならない
- 設計・開発する者の責任である
- あらかじめ確認する必要がある
アクセシビリティ・サポーテッドとは? †
- 利用者の支援技術によってサポートされている技術
- 利用者が入手可能で、利用できるUA(ユーザエージェント)がある
以下の4つのうち少なくとも1つを満たす必要がある
- 広く配布されているユーザエージェントでサポート
- 広く配布されているプラグインでサポート
- (大学、イントラなど)閉じた環境で利用可能なUAでサポート
- 障害のある人でも容易に手に入れられるUAでサポート
アクセシビリティサポーテッド情報の一覧(英語)
http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20/implementation-report/html-uses-table
課題 †
- 推奨する実装方法を統一見解として提示したい(ただし未着手)
- 何をもって「アクセシビリティ・サポーテッド」とみなすか
- ブラウザ・支援技術・バージョン…
- 海外と日本の違い
- Techniqueは案外記述がいい加減で大変。。
- 海外でWCAG2.0に対応したサイトは聞かない…
- 英語圏はJAWS対応ならOK、が暗黙の了解
- 日本はガイドラインでなくJIS=規格なので
改正版JISの試験方法 †
梅垣正宏(日本障害者協議会)さんの個人的意見も含む、と前置きでの説明
- 啓蒙啓発の時代(2004)から試験・評価の時代(2010)へ
- チェックは1ページ1~2時間くらいかかる
- ツールだけではチェックできない
- 検出率50%、という数字も
- 自己適合宣言(Q1000)
- 試験、測定方法を明確に
- ページ全体が試験にクリアしないといけない
- ページの一部だけ、はNG
- フォームであれば、入力→確認→完了の「プロセス全体」が対象
- リンクは含まない
- 「測定」「自動化試験」「観察」「資料的論拠」「専門家評価」「ユーザ評価」
- 「資料的論拠」…テンプレートなどを使用していて、すでにほかの試験でクリアした場合
以下は渡辺昌洋さんの説明より。
| 達成基準リスト | 作成、表示必須 |
| 実装チェックリスト | 作成必須、表示は任意 |
- 実装チェックリストひな型を現在作成している
- 使用されていない実装方法と達成基準は書かなくてよい
- 対応するJIS項目番号を書くなど…
まとめと感想 †
- 今回のJISは、testableということで「ちゃんとやっていることがわかるようになっている」ので、ちゃんとやっている会社や個人がわかってしまう。→ちゃんとやっていることをアピールできる。
- WCAG2.0があるとはいえ、周辺文書の整備が膨大で大変みたいです…
英語が得意だったらなぁ…
- しかしこれが整備されれば、いままでにない素晴らしいリファレンスになるので、
制作者の知識のバラツキや負担が減って、実装状況も改善されると思う。
(世の制作者はIE6だけでもウンウン言ってる現状なので…)
コメントをどうぞ †
- コンテンツ制作者の立場からは、JIS規格として、前提ブラウザを特定(明示)すべきと考えます。表示にバグがあるブラウザでの正しい表示を求めることが間違っており、HTML、CSS、Javascriptの文法に対して正しく動作するブラウザを指定し、そのブラウザでのコンテンツの評価を行うべきである。アクセシビリティを重視するハンデキャッパーはJIS規格に準拠したブラウザを使いなさい!とした上で、コンテンツ制作者はJIS規格に準拠したコンテンツを制作するべきなのです。例を挙げれば、IE6では正しく表示されなくてもコンテンツの責任では無いということです。バグがあるブラウザを使用している人が悪いのです。他の業界に置き換えたら分かりやすいのですが、欠陥車を運転して事故を起こした際に、「運転が下手だったから」とドライバーを責めるよりも欠陥車そのものが非難を浴びますよね。一方的にコンテンツ制作者に負担があるJIS規格だったら無いほうがマシです。 -- 石井? 2010-02-09 (火) 18:04:36
- 実際に使用されているユーザ(障害者を含む全ての人)の環境を考慮しなけらば絵空事でしょ。 -- msuzuki? 2010-04-22 (木) 12:26:42
tag: JIS X 8341-3