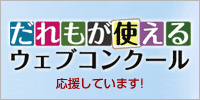アクセシビリティメモ/「JIS X 8341-3」を読む(1) http://www.ark-web.jp/accessibility/154.html
アクセシビリティメモ/「JIS X 8341-3」を読む(1)このページは? †
高齢者・障害者等配慮設計指針─情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス─
第3部;ウェブコンテンツ (JIS X 8341-3)
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=jp&bunsyoId=JIS+X+8341-3%3A2004&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0
- 2008年9月8日(月)、スタッフのアクセシビリティのリテラシーを上げるため、JIS X 8341-3を皆で読み、議論する会を社内で行った。
- 参加者:中野, 野島, 進地, 竹村, 八木, 志田
- 文責:中野
議論 †
- JIS X 8341-1は「共通指針」、JIS X 8341-2は「情報処理装置」、JIS X 8341-3は「ウェブコンテンツ」を扱っているんだね。「共有指針」も余裕があれば読んだ方がよさそう。
- 4.3 a)の「認知及び記憶への過度な負荷をかけずに」を筆頭に、認知に問題がある人への配慮についての記述が結構多いと思った。
- 5.2 a)の「参考」で言及されている、リスト表示の“・”、“※”などはやってしまうことが多いかも。注意しないと。
- 「※」は「【注意】」のなど意味で使うことが多いから、ちゃんと言葉で書くべきだろう。
- 5.2 g)の例3、headセクション内のlink要素にindex、prev、nextなどのリンク型、意識してマークアップしている?
- 対応していると、Operaなどではナビゲーションが対応しているから便利。
- CMSなどでは対応しているケースも多い。Movable Typeのデフォルトテンプレートにも記述されている。
- 5.3 b)の例4、選択肢の構造化、親選択肢に応じて子選択肢の内容が変わる場合、5.3.a)を考えると実行ボタンがあった方がいいのでは?
- 5.3 d)の「時間延長」、セキュリティ問題が気になるところ。「時間延長」を押しまくるスクリプトをまわしながらアタックをかけるとか?
- 「ログイン状況」を出しておくのは、勝手にログアウトさせられることを嫌う健常者のユーザビリティ向上にも役立つんじゃないかな?
- 時間制限については、Zen Cart(ECソフトウェア)でもきちんと考慮しなきゃね。サイト上にポリシーを書いておく、残り時間を示す、延長ボタンをつけるとか。
- 5.3 e)、Yahoo!などのスポーツ中継のページには自動更新をやめることができる機能がある。
- 止める、履歴を見ることができるなどがベターでは。
- 5.3 i)、誤った操作について、付属書には「確認メールを出す」などの例もあるね。
- 5.4 d)の参考、動画への字幕や状況説明(ナレーションなど?)は、「認知又は記憶に障害がある場合」にも役立つというところ、なるほど。
- 5.7 a)、Flashコンテンツなど、音が自動的に再生されているが、わかりづらいケースは実際には多いよね。Flashはデザインが凝っているケースも多いし。
- 5.8 b) 例2、しま、渦巻き、同心円などの規則的パターン、確かに健常者でも気分が悪くなることがある。注意すべきだろう。
- 5.9 a) 例2、自然言語が切り替わるすべての箇所でp要素、q要素、span要素などで明示すべき、ってホント?
- 明示的に指定しておくと、音声ブラウザでの読み上げ音声が違うはずです。
- 明示的に指定した場合にいろんな音声ブラウザでどうなるか、試してみたいな。
- 6.1 例1「ウェブコンテンツを自動的に生成するプログラムには、アクセス可能なウェブコンテンツを生成する機能を装備する」は特にWebアプリを作る人にとって重要!
- 6.2 の参考、「ウェブブラウザなどのウェブ技術の進歩に対応し」は、できていないことが多いなぁ。
- ターゲットブラウザって下限の話はするが、「IE8が出たから積極的に対応しましょう」みたいな話はあんまりしないからなぁ。
コメントをどうぞ †
tag: JIS X 8341-3